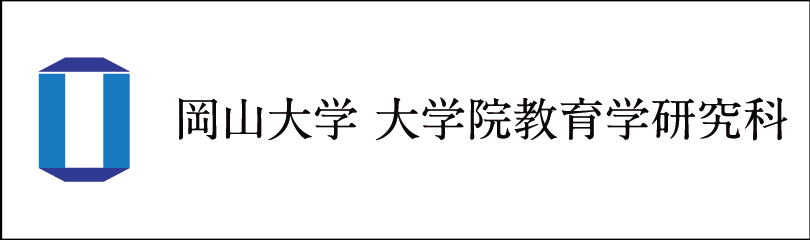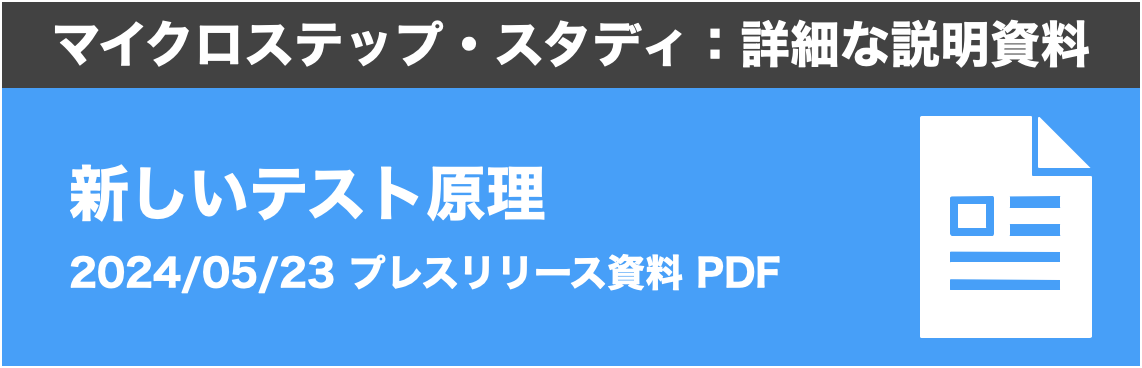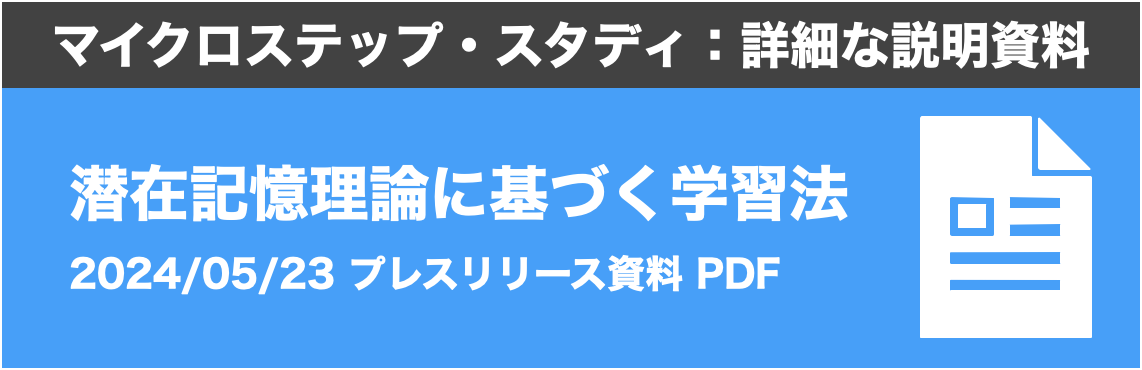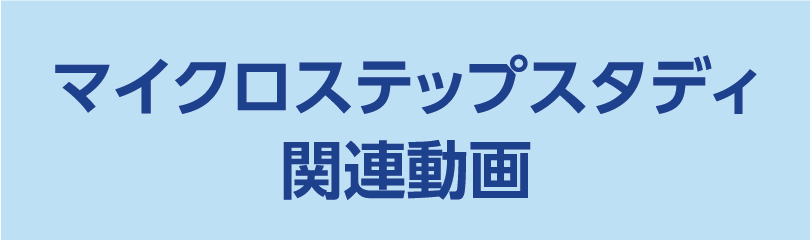感覚記憶の長期持続性
記憶には自信がない、忘れっぽい、など、私たちが持つ一般的な記憶のイメージは、どちらかというとネガティブなものかもしれません。しかし、私たちは様々な情報を大量に、そして詳細に記憶として保持できることが知られています。
人間の記憶は、その内容について「思い出す」という意識が生じているか否かという基準で、顕在記憶と潜在記憶に区分することができます。思い出すという意識が生じている場合は顕在記憶、そのような意識が生じない場合には潜在記憶とよびます。記憶実験において、覚えるべき項目を学習したあと、顕在記憶を測定してみると、学習直後から時間が経過するごとに記憶課題の成績は顕著に低下していく様子がみられます。一方、潜在記憶を測定すると、時間経過に伴う成績の減衰は少なく、一定したパフォーマンスが長期にわたり保持されている様子がみられます。このような現象は、英単語や日本語の単語といった言語刺激のほか、日常にある物体や人の顔の線画といった非言語刺激を用いた場合にも確認されています。つまり、私たちは意識できないレベルで様々な情報を長期にわたり記憶として保持し、利用していると考えられます。
私たちの研究室では、ランダムに作成された音列刺激や、概念情報に乏しい視覚刺激など、言語的符号化が困難な刺激を用いて潜在記憶の特徴を調べています(e.g. 益岡・西山・寺澤, 2018; Nishiyama & Kawaguchi, 2014; 寺澤, 2001; 上田・寺澤, 2008, 2010)。複数の研究結果から、「覚えよう」という意識が生じない状況であっても、わずか数秒程度、対象の刺激と接触するのみで、その刺激の詳細な情報が数か月以上は保持されることが確認されています。一般的に、ある情報を長期記憶として保持するためには、何度もその情報を繰り返すことや、自分がすでに知っている他の事柄との関連付けなど、何らかの意味づけを行うことが有効だと考えられています。しかし、潜在記憶に関する研究結果から、私たちはある情報に注意を向けた時点で、その情報を長期記憶として保持することが可能であり、さらに保持しているそれらの情報を瞬時に利用するメカニズムが備わっていることが考えられます。私たちはこのような人間の記憶の特性について調べるとともに、そのメカニズムに関する理論構築を行っています。
関連する一般書
- 寺澤 孝文 (2001). 記憶と意識―どんな経験も影響はずっと残る― (第5章) 森 敏明 (編著) 認知心理学を語る①:おもしろ記憶のラボラトリー (pp.101-124) 北大路書房
関連する論文:
- 益岡 都萌・西山 めぐみ・寺澤 孝文 (2018). 視覚的記憶の長期持続性と変化検出過程への影響 心理学研究, 89, 409-415.
- Nishiyama, M., & Kawaguchi, J. (2014). Visual long-term memory and change blindness: Different effects of pre-and post-change information on one-shot change detection using meaningless geometric objects. Consciousness and Cognition, 30, 105–117.
- 上田 紋佳・寺澤 孝文 (2008). 聴覚刺激の偶発学習が長期インターバル後の再認実験の成績に及ぼす影響 認知心理学研究, 6, 35-45.
- 上田 紋佳・寺澤 孝文 (2010). 間接再認手続きによる言語的符号化困難な音列の潜在記憶の検出 心理学研究, 81, 413-419.